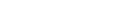新しく犬を迎え入れられた方は去勢・避妊手術をするかどうか悩まれると思います。
また、ある程度歳をとった子に対して手術をすべきかどうか悩まれている方も多いのではないでしょうか。
今回は基本的な去勢や避妊についての解説と当院の方針について以下で詳しく解説します。
犬の去勢手術とは
犬の去勢手術とは精巣摘出という手術のことを指します。
ほとんどの動物病院では陰茎の直上で皮膚を切開し、1箇所の傷から2個とも精巣を摘出する方法を採用しています。
犬の去勢手術のメリットは?
犬の去勢手術のメリットは多く存在します。
マーキングの減少、喧嘩のリスクの低下、望まぬ繁殖の防止といった行動に関連するメリットがまず挙げられます。
これらのメリットは若いうちに手術を実施した方がその恩恵を受けやすいため、若いうちに去勢手術を実施する根拠になります。
もう1つのメリットは病気の予防です。
以下のような病気が高齢かつ未去勢だと発生することがあります。反対に、高齢になるまでに去勢を実施することでこれらの病気になる確率を大きく下げることができます。
肛門周囲腺腫
肛門の周りに発生することが多い良性腫瘍です。大きくなってしまうと手術が必要なこともあります。
言葉が似ている病気に肛門周囲腺癌と肛門嚢アポクリン腺癌がありますが、これらは去勢手術をしてもしなくても発生率が変わらないと言われています。
前立腺過形成
前立腺が大きくなる病気です。前立腺の近くには直腸があるため、排便が困難になることがあります。他にも前立腺に感染が起きてしまい、前立腺炎と呼ばれる病気になることもあります。
前立腺癌という病気もありますが、こちらは去勢手術と病気の発生率に関連はありません。
会陰ヘルニア
お尻の筋肉が薄くなり、裂けることによってお腹の臓器が皮膚の下に飛び出てしまう病気です。
手術で治療を行うことになります。
犬の去勢手術のデメリットは?
犬の去勢手術にはデメリットもあります。
もちろんメリットがデメリットを上回るので手術を実施しているのですが、デメリットを正しく認識しておくことは非常に大切です。
肥満
最もよくみる去勢のデメリットです。
去勢を行った犬は、代謝の変化や行動の変化などにより太りやすい体質になると言われています。
そのため、術後は去勢・避妊済みのご飯などでカロリーをコントロールすることが大事になります。
麻酔のリスク
多くの方が最も気にされるデメリットです。
詳細については別のページで詳しく解説をしているのでそちらをご覧ください。
若くて健康な子の麻酔リスクは0.05%未満と言われています。
この数字は大きいか小さいかは人によって見方が異なるとは思いますが、多くの獣医師はこのリスクであれば去勢手術のメリットが大きいと判断して手術を行なっています。
犬の去勢手術の時期は?
実は去勢手術に最も適した時期というのは決まっていません。
また、近年は大型犬は早めの去勢手術は避けるべきというデータが出ています。
当院では小型犬種は6ヶ月頃、大型犬種は1歳ごろを目安に、色々な事情を加味して実施日を決定しています。
ラハ動物病院での去勢手術の流れ
よくある若い犬の去勢は以下のような流れで行います。
術前検査
麻酔をかけても良いかどうかの検査を行います。
基本的には8時間以上絶食して検査をすることが望ましいため、朝ごはんを抜いてきていただくことが多いです。
何らかの事情により絶食が難しい場合、検査の日程の都合がつかない場合は、中止の可能性をご理解いただいた上で手術日に検査を行うこともあります。
手術日
12時間絶食をした上で午前中の診察時間に来院していただきます。
来院後は当日の流れをご説明した上で、院内にてお預かりさせていただき、ご家族の方には一度ご帰宅いただきます。
12〜13時ごろから鎮静・麻酔を実施し、手術を開始します。
手術は30分ほどで終了することが多く、麻酔から覚めたあとは入院室で経過を見ます。
午後の診察時間で退院です。
この際、抜糸まで傷の保護が必要なのでエリザベスカラーもしくはエリザベスウェアを着用してもらいます。
抜糸
手術日から10〜14日後抜糸を行い、完全に終了です。
ラハ動物病院の去勢手術に対する方針
当院では去勢手術をおすすめしております。
また、何らかの事情により若いころに去勢手術を行っていない子についても去勢手術をおすすめしております。
去勢手術をしない状態で高齢になった場合、上記のような病気になることが多いのですが、結局去勢手術の実施により治療する例が多くあります。
そのため、より高齢になり併発疾患などのリスクを抱えた状態で手術を行うよりは、今実施したほうがリスクも少なく体への負担も少ないであろうと考えています。
犬の避妊手術とは
犬の避妊手術は大きく分けて2つの方法があります。
1つは卵巣のみ切除する方法であり卵巣摘出術と呼ばれます。
もう1つは子宮と卵巣を切除する方法であり、卵巣子宮摘出術と呼ばれます。
どちらを実施するかは色々な事情をから決まってはくるものの、当院では子宮卵巣摘出術を主に行っています。
また、当院を含むほとんどの病院は開腹して手術を行いますが、一部病院では腹腔鏡を用いた手術を行っています。
当院でも体格の大きな子は腹腔鏡手術を行うメリットが高いと考えているため、おすすめする場合があります。
犬の避妊手術のメリットは?
犬の避妊手術の1番のメリットは病気の予防です。
乳腺腫瘍や子宮蓄膿症といった病気の発生率が未避妊の子では明らかに高く、これらの病気は命にかかわる場合もあります。
そのため早期に避妊手術を実施するメリットは非常に大きいと考えられます。
子宮蓄膿症
子宮に膿が溜まる病気です。
避妊手術をしていない犬は10歳までに25%の確率で子宮蓄膿症になるというデータも出ており、非常に多く発生する病気です。
詳しくは以下のページで解説しています。
乳腺腫瘍
乳腺にできる腫瘍の総称です。
悪性のものは乳がんと呼ばれます。
未避妊の子で多く発生することが知られており、避妊の実施時期で病気になる確率が変わるとも言われています。
治療は基本的に外科手術により行い、同時に避妊手術を実施することも多くあります。
犬の避妊手術のデメリットは?
肥満のリスク、麻酔のリスクについては去勢手術と同様です。
他には、早期(3ヶ月齢未満)で手術をした場合明らかに尿失禁が増えるという報告や、大型犬は時期が遅くても尿失禁を発症するリスクがあると言われています。
犬の避妊手術の時期は?
犬の避妊手術の実施時期は4~6か月ごろが望ましいと言われています。
当院では小型犬が多い日本ではよく遭遇する乳歯遺残のことも考え、6ヶ月ごろでの避妊手術をおすすめしています。
また、6か月ごろでは初回の発情が起こる子も出てきます。
発情が来てしまった子たちについては最低でも1ヶ月の延期をお願いしています。
よく「初回発情前に手術をした方が良いと聞きましたが、発情が来てしまいました」と悲しまれるご家族の方がいらっしゃいます。
確かに当院でも初回発情前にできた方が良いとは考えています。
しかし、この根拠となっている報告は1960年代のものであり、現代とは色々と異なる点もあります。
そのため、初回発情が来てしまったらしょうがないくらいの気持ちで過ごしていただく方が良いのかなと考えています。
ラハ動物病院での避妊手術の流れ
よくある若い子の避妊手術は以下のような流れで行います。
術前検査
麻酔をかけても良いかどうかの検査を行います。
基本的には8時間以上絶食して検査をすることが望ましいため、朝ごはんを抜いてきていただくことが多いです。
何らかの事情により絶食が難しい場合、検査の日程の都合がつかない場合は、中止の可能性をご理解いただいた上で手術日に検査を行うこともあります。
手術日
12時間絶食をした上で午前中の診察時間に来院していただきます。
来院後は当日の流れをご説明した上で、院内にてお預かりさせていただき、ご家族の方には一度ご帰宅いただきます。
12〜13時ごろから鎮静・麻酔を実施し、手術を開始します。
手術は1時間ほどで終了することが多く、麻酔から覚めたあとは入院室で経過を見ます。
基本的には18時以降に退院です。
この際、抜糸まで傷の保護が必要なのでエリザベスカラーもしくはエリザベスウェアを着用してもらいます。
抜糸
手術日から10〜14日後抜糸を行い、完全に終了です。
ラハ動物病院の避妊手術に対する方針
当院では避妊手術を強くおすすめします。
避妊手術を行わなかった場合、子宮疾患が高率に発生することと、子宮蓄膿症であれば救急対応が必要なことが大きな理由です。
子宮蓄膿症になった場合の手術は通常時の手術よりもリスクが大きくなり、入院期間も伸びるため、負担が大きくなりがちです。
子宮蓄膿症になられたご家族は、もっと早く避妊手術をしておくべきだったと言われる方が多い印象があります。
若い子に手術を実施することに関して不安もあるかと思いますが、ぜひ一度ご検討ください。

 診察時間
診察時間 アクセス
アクセス
 2025.07.09
2025.07.09